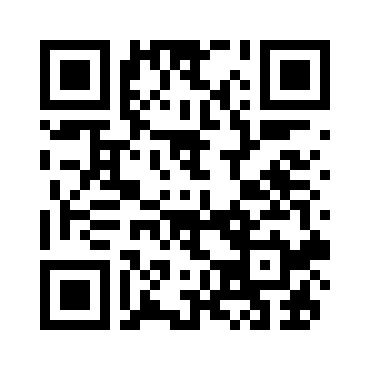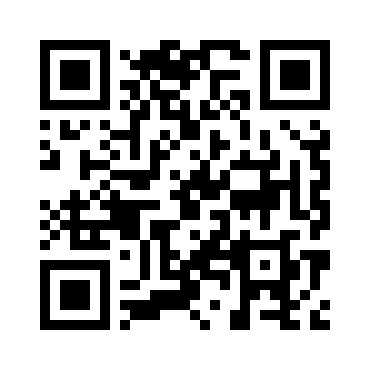11 minits
向上心のある20〜40代の皆様、日々の仕事やキャリア形成において、「本当にこれで良いのだろうか」と立ち止まる瞬間はありませんでしょうか。
「好き」という感情が、実はあなたの人生を大きく変える羅針盤になる――
そんな深い洞察について、今回は楠木建氏の著書「すべては『好き嫌い』から始まる」を紐解いてまいります。
単なる「好きなことを仕事にしよう」といった甘い話ではありません。
競争が激化する現代において、どのようにすれば唯一無二の存在となり、真に充実したキャリアを築けるのか。
その本質的な思考法を、記憶に深く刻み込んでいただけるよう、丁寧にご紹介いたします。
Contents
プロになるなら仕事が好きである必要があります。

プロフェッショナルとして一流を目指すならば、その仕事自体を心から好きであることが不可欠です。
なぜなら、「好き」という感情は、私たちに圧倒的な持続力をもたらすからです。
好きなことには、時間を忘れて没頭できますね。
他人から評価されなくても、すぐには結果が出なくても、ワクワクしながら自発的に探求し続けることができるのです。
このような継続こそが、最終的に他の人には真似できない「特殊能力」を身につけることにつながります。
この特殊能力こそが、激しい競争社会で勝利するための「決定的な違い」を生み出す源泉となるのです。
逆に、好きではないことを続けるのは苦痛であり、努力が必要になります。
結果が出なかったり、周囲からの評価が得られなくなったりすると、すぐにやめてしまう傾向があるでしょう。
これでは、何年もかけて独自の能力を磨くことはできません。
楠木氏は「努力しなきゃと思った時点で、そもそも向いていないし、他との違いを作るほど極めることができない」と指摘しています。
ただ生活のためだけに仕事をするのであれば、言われたことをこなすだけで十分かもしれません。 しかし、それでは「替えが効く」存在にとどまり、大きな価値を生み出すことは難しいでしょう。
他の人ができないことを一つでもできるようになれば、あなたは替えの効かない存在となり、計り知れない価値を生み出すことができるのです。
そのために、自分の「好き」をシンプルに突き詰めることが何よりも大切になります。
自分の「好き」を優先し、その後に「お客さんがいいと思うこと」をすり合わせましょう。

「好きなことを仕事にできるのは一握りの人だけ」「好きなことは趣味でやればいい」という意見を耳にすることがありますね。
確かに、仕事とは基本的に「自分以外の誰かのためにやる活動」であり、お金が入ってくれば仕事、入らなければ趣味というのが一般的な考え方です。
だからこそ、多くの人は自分の好き嫌いよりも「お客さんが何を求めているか」に意識が向きがちです。
流行っているからとタピオカ屋を始めたり、儲かりそうだからとYouTubeで特定の動画を投稿したりするようなものです。
しかし、これでは短期的な成果は出ても、長続きはしません。
なぜなら、他との違いを生み出せず、好きではないために続けることが苦痛になり、少しでもうまくいかないとすぐに諦めてしまうからです。
そこで楠木氏は、まず最初に自分が好きなことを追求し、その後に「お客さんがいいと思うこと」を追求していく、という順番が重要だと述べています。
この二つをいかに上手にすり合わせるかが、仕事の醍醐味なのです。
まるでアーティストが、まず自分の好きな曲を作り、その後にお客さんに響く曲を追求していくようなものですね。
この順番を意識することで、あなたの「好き」がビジネスとして花開く可能性がぐっと高まるでしょう。
自分の「好き嫌い」を小さく分解して言語化しましょう。
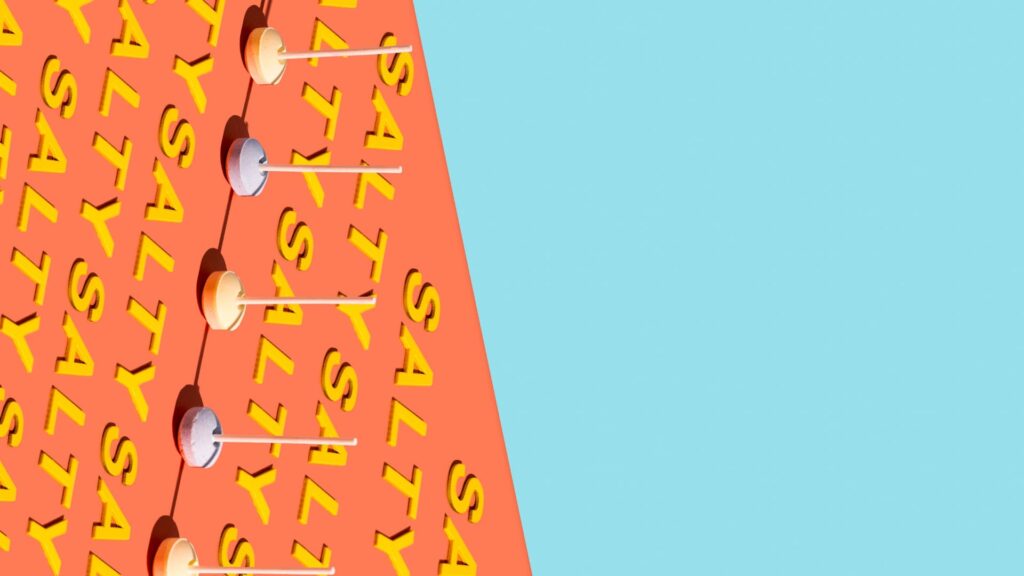
「好きを追求しろ」と言われると、すぐに「夢を追いかけろ」というメッセージだと捉えてしまうかもしれません。
しかし、楠木氏が言いたいことはそれとは少し異なります。 プロ野球選手や人気YouTuberを目指すことも素晴らしいですが、正直なところ、努力だけではどうにもならない現実もあります。
では、どうすれば良いのでしょうか。
大切なのは、自分が「なぜ好きなのか」「なぜ嫌いなのか」という問いを立て、その理由を細かく分解して言語化することです。
たとえば、「給与が高いから好き」「一人で作業するのが好き」「集団での仕事は嫌い」「上下関係は嫌い」「体を動かすのが好き」など、具体的な要素に落とし込んでみるのです。
もしあなたが「人と対戦して勝ち負けがあることが好き」だとすれば、固定給の仕事よりも、成果によって報酬が変わる歩合制の仕事やフリーランスが向いているかもしれません。
「人と一緒に仕事をするのが嫌いで、あれこれ指図されたくない」のであれば、一人でできる仕事、例えばタクシー運転手やクリエイティブな仕事が選択肢に入ってくるでしょう。
重要なのは、ゲーム実況者であることにこだわるのではなく、あなたの「好き」を構成する要素を満たす別の仕事を探すことです。
楠木氏自身も、お金にならない音楽は趣味として続け、書くことを仕事にしていると語っています。
私たちは言葉でしか考えることができません。
だからこそ、自分の好き嫌いを具体的に言語化しておくことで、仕事だけでなく人生全般において、より満足度の高い選択ができるようになるのです。
無意識に感じている好き嫌いを意識的に分解し、言葉にすることで、あなたの選択基準は格段に明確になるでしょう。
想像するのではなく、さっさと経験しましょう。

何事も、実際にやってみなければ「好き」か「嫌い」かは分かりません。 頭の中で想像していたことと、現実が大きく異なることはよくあることです。
YouTubeに憧れる人が多い一方で、実際にやってみたら想像と違って嫌になったり、伸びると思ったのに伸びなかったりすることもありますね。
楠木氏の著書では「10時間の想像よりも1分の実体験が大事」だと書かれています。
未知のことについてあれこれ考え込むよりも、「とりあえずやってみるか」という姿勢で生活することが推奨されているのです。
もちろん、想像力も大切です。
しかしそれは、経験した後に良い想像をするためのものであり、経験なしに良い想像はできないという順番の問題なのです。
まずは小さくても良いので、実際に一歩を踏み出し、経験してみることを強くお勧めします。
そうすることで、あなたの「好き嫌い」はより明確になり、次の行動へと繋がっていくでしょう。
多分最初は失敗するだろうと考えて挑戦しましょう。

何か新しいことに挑戦する際、「最初からうまくいくはずだ」と期待しすぎると、無用なプレッシャーがかかり、小さな失敗で心が折れてしまいがちです。
私たちは、一度の失敗で挫折したり、失敗を恐れて行動できなくなってしまうことがあります。
しかし、特にビジネスの世界では、成功よりも失敗の方がはるかに多いのが現実です。
ユニクロの柳井正氏の著書名が「一勝九敗」であることや、建築家の安藤忠雄氏の著書名が「連戦連敗」であることからも、その真理が伺えますね。
失敗は当たり前、むしろ基本だと考えるべきなのです。
それでも、やってみなければ結果は分かりませんし、学びも得られません。
だからこそ、「多分最初は失敗するだろうな」というくらいの軽い気持ちで挑戦することが大切です。
この「楽観的悲観主義」という考え方は、うまくいかなくてもそこまで落ち込まずに済み、何度も挑戦し続けることを可能にします。
そして何より、予想外にうまくいった時には、より大きな喜びを感じることができるでしょう。
一度や二度の失敗で心が折れないためにも、この思考法をぜひ取り入れてみてください。
好きなことをやっていること自体がご褒美になります。

好きなことを続けていると、たとえ結果がどうであれ、そのプロセス自体が大きな喜びとなります。
時間を忘れて夢中になれること、それ自体があなたにとってのご褒美となるのです。
阪神ファンが勝敗に関わらず応援を楽しんでいるように、好きなことは結果が出なくても、その過程を楽しむことができるのですね。
この本の著者である楠木氏も、文章を書くこと自体が好きであるため、たとえ本が売れなくても「別にいいや」と思えるそうです。
もちろん結果が出た方が嬉しいのは当然ですが、結果はなかなか自分ではコントロールできないものです。
だからこそ、過程を楽しめるかどうかは、人生の幸福度を大きく左右する重要な要素となるでしょう。
「結果が出ないと続けたくない」と感じるなら、それは本当に好きではないのかもしれません。
あなたの「好き」が、日々の生活をより豊かにするご褒美となることを知ってください。
好きなことをやっていると、相手の「好き」も尊重できるようになります。
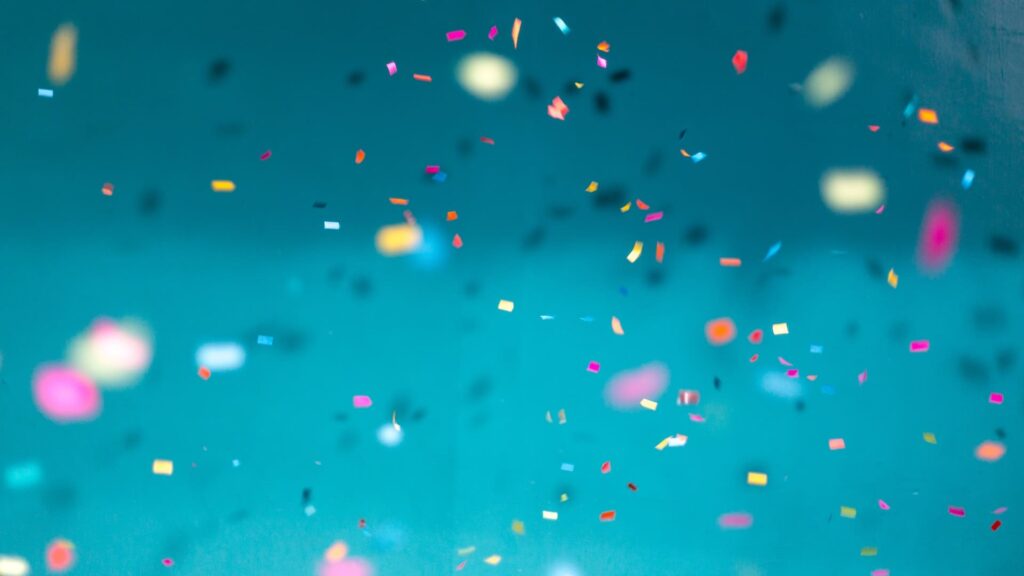
自分が好きなことをしている時、他人が好きなことをしていても、特に嫌な気分にはなりませんよね。
「自分も好きなことをしているのだから、相手も好きなことをしているのだろう」と自然に思えるものです。
しかし、もし自分が好きでもないことを強制的にやらされている状況だったらどうでしょうか。
相手が好きなことを楽しんでいる姿を見ると、「自分は我慢しているのに、なぜあの人だけ好きなことをしているんだ」と、ずるいと感じたり、腹立たしく思ったりしてしまうものです。
これは、仕事においても全く同じことが言えます。
自分が好きな仕事をしている時、他人が好きなことをしているのも許容できます。 しかし、嫌いな仕事をさせられていると、他人にも嫌なことを我慢させて、やらせたくなってしまう傾向があります。 かけがえのない人生だからこそ、自分の好きなこと、少なくとも嫌いではないことを仕事にできると良いですね。
自分の「好き」を追求することは、他者の「好き」を尊重する心の余裕を生み出すことにも繋がるのです。
自分の「好き」を追求すれば、必ず誰かからは嫌われます。

自分の好きなものを深く追求していくと、だんだんと個性や色が明確になってきます。
そうすると、それが「嫌い」だと感じる人からは、より一層嫌われやすくなるものです。
人気のあるユニクロやくら寿司、ラーメン二郎でさえも、こだわりを持つ人や健康を気にする人からは敬遠されることがありますね。
誰かから深く好かれるということは、別の誰かからは深く嫌われることと同義である、と楠木氏は語っています。
だからこそ、自分の「好き」を追求し、表現する際には、むしろ「誰に嫌われるのか」を明確にした方が良いと提言しています。
そこにこそ、商売の生命線があるというのです。
大切なのは、すべての人に好かれようとするのではなく、「分かってくれる人にだけ分かってもらえればいい」という割り切った姿勢を持つことなのですね。
自分の「好き」を貫くことは、あなたが真に価値を提供すべき対象を明確にすることにも繋がるでしょう。
まとめ:知識を定着させる最後のインプット

ここまで、楠木建氏の「すべては『好き嫌い』から始まる」を基に、仕事における「好き嫌い」の重要性と、それをキャリアに活かすための思考法について深掘りしてきました。
- ビジネスで競争に勝つためには、競合他者との決定的な違いを作ることが不可欠です。
- その違いは、長期間の努力によってのみ身につけることができます。
- 長期間努力し続けるためには、自分の好きなことを突き詰めるしかありません。
- だからこそ、その業界でプロを目指すなら、仕事が好きである必要があります。
- しかし、好きでもお客さんに評価されなければ仕事とは言えません。
そこで、まず自分の「好き」を優先し、その後に「お客さんが良いと思うこと」と上手にすり合わせることが大切です。 - それでも好きなことで生計を立てられない場合は、一つの仕事にこだわる必要はありません。
- 日頃から自分の好き嫌いについて「なぜ好きなのか」「なぜ嫌いなのか」という問いを立てて言語化し、その要素を満たす他の仕事を探す柔軟性が重要です。
- 何事もやってみなければ分からないため、想像するのではなく、さっさと経験する姿勢を持ちましょう。
- 最初から成功を期待するのではなく、「多分最初は失敗するだろう」と考えて挑戦する「楽観的悲観主義」の考え方が、継続と成功への鍵です。
- 好きなことをやっていることには、結果がどうであれ、毎日やっていること自体がご褒美になるという大きなメリットがあります。
- また、好きなことをしていると、相手の「好き」も尊重できるようになるという人間関係におけるメリットも生まれます。
- そして最後に、自分の「好き」を追求し表現することは、必ず誰かからは嫌われることになります。
むしろ、「誰に嫌われるか」を明確にすることが、ビジネスにおいては極めて重要なのです。
「好き」という感覚は、お金では買えない、あなたの最も強力な羅針盤です。
この感覚こそが、最終的に大きな価値を生み出す源泉となるでしょう。
今回の学びが、皆様のキャリアや人生をより豊かにする一助となれば幸いです。
ぜひ何度も読み返し、ご自身の「好き嫌い」を見つめ直すきっかけにしてください。

「貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する」は、お金に関する常識を覆し、新たな生き方を提示する。この記事では、本書で紹介される実践的な方法を通じて、豊かさを手にするステップを具体的に紹介します。
貧乏から豊かさへ、「雇われない生き方」で格差社会を超越する方法

あなたは『原因自分論』という考え方をご存知でしょうか?『原因自分論』という考え方は、悩んでいる物事を好転させるきっかけになる考え方です。この考え方を身に付けることができればストレスなく生きていけることはもちろん、人間関係、会社の業績、その他いろいろな物事をより良い方向に近づけていけます。
あなたを救う『原因自分論』という考え方。

多くの20代は"あれも欲しい"、"これもやりたい"とむやみに選択肢を増やして、本来必要でないことにまで貴重な時間やお金を浪費しているのではないでしょうか? そしてその全てを大事にしようとして、いろいろなものを捨てられなくなり、結果として雁字搦めになってしまっています。 本記事では自由な生き方を失わないために捨てるべきことが分かりやすく解説しています。
20代で捨てるべきもの・考え方 “8選”

『サイコロジー・オブ・マネー』は、お金に対する心構えや行動がどのように「富」に影響を与えるのかを深く探ります。本記事ではそのエッセンスを要約し、長期的に財産を築くための心理的アプローチを説明します。