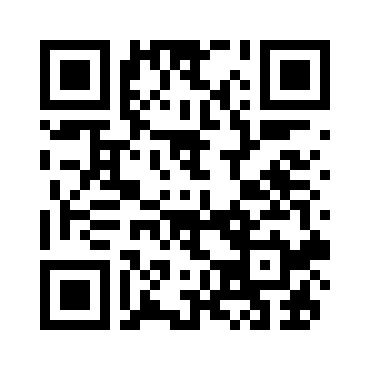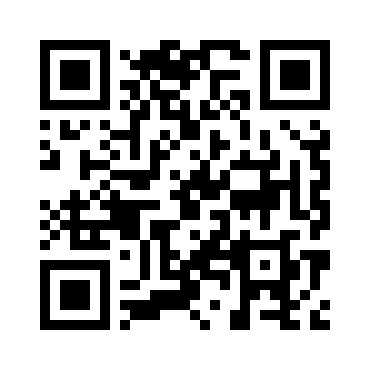9 minits
向上心のある20代から40代の読者の皆様、日々のマネジメント業務、お疲れ様です。
チームを率いる立場として、部下の育成やプロジェクトの成功に日々尽力されていることと思います。
しかし、良かれと思って行っているマネジメントが、実は部下の心身を疲弊させ、チーム全体のパフォーマンスを低下させている可能性に気づいていますか?
今回は、長年プロジェクトマネージャーを務めてこられた橋本正吉さんの著書『人が壊れるマネジメント』を参考に、部下を「壊してしまう」典型的なマネジメントの落とし穴について深く掘り下げていきます。
この本は、私たちが陥りがちな「間違ったマネジメント」のパターンを具体的に教えてくれます。
本記事が、皆さんのマネジメントを再考し、チームをより強く、そして部下との信頼関係を深めるための「記憶に定着する備忘録」となることを願っています。
Contents
部下を壊す「ダメなマネジメント」8つのパターン
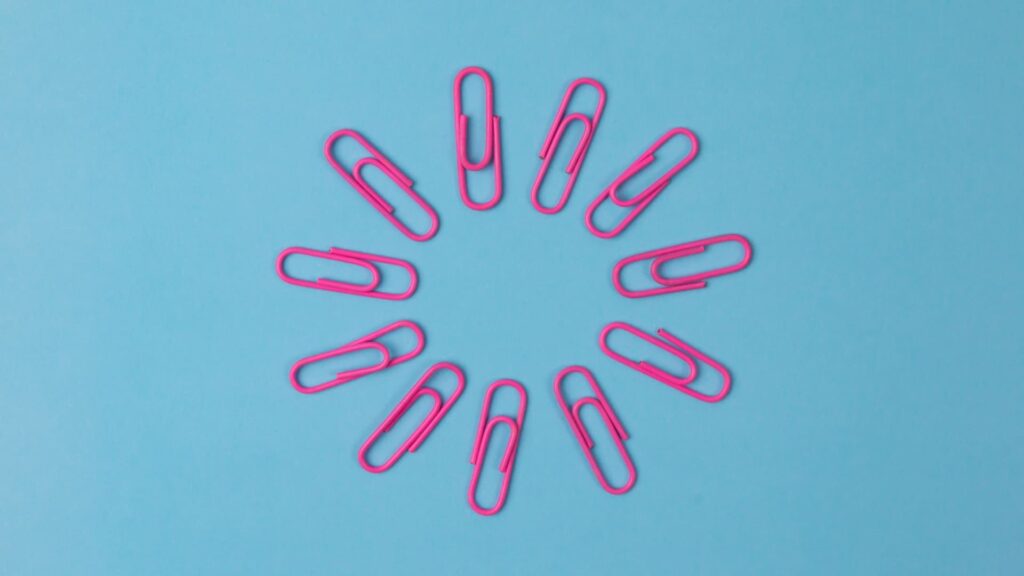
マネージャーは、上層部が定めたゴールに向かって、部下、時間、お金、スケジュールといったリソースを管理し、チームを引っ張っていく現場のリーダーです。
非常に重要な役割である反面、多くのプレッシャーの中で、意図せず不適切なマネジメントに陥ってしまうことがあります。
そうした「ダメなマネジメント」が続くと、部下のメンタルが壊れたり、突然の退職につながったり、ひいてはプロジェクトそのものが失敗に終わることも少なくありません。
ここでは、そうした事態を避けるために、特に注意すべき8つのパターンと、それぞれの改善策について見ていきましょう。
1. 曖昧な指示でタスクを丸投げしていませんか?

「全体的に任せるから、いい感じに仕上げてくれる?なるべく早くお願いね」といった、ふわっとした指示。
これ、部下にとっては非常に困惑するものです。
上司としては「任せている」つもりでも、部下は「結局、いつまでに、どんなものを作ればいいのか」が分からず、手探りで仕事をすることになります。
その結果、「なんか違うんだよな」と上司に言われてしまい、部下は「それなら最初に言ってくれよ…」と不満を抱えてしまうのです。
改善策:
指示を出す際は、できるだけ曖昧さを排除し、具体的に伝えることを意識しましょう。
特に「6W2H」(誰が、何を、いつ、どこで、誰に、なぜやるのか、どのように、いくらで)を明確にすることで、部下との認識のズレを最小限に抑えられます。
例えば、「なるべく早く」ではなく「〇月〇日15時までに提出」と具体的に納期を伝えるだけで、部下の行動は大きく変わるはずです。
もしマネージャー自身も具体的なイメージが固まっていない場合は、部下と相談しながら方向性をすり合わせる時間も重要です。
2. 部下を縛り付けるマイクロマネジメント

マイクロマネジメントとは、上司が部下にべったりと張り付き、業務の細かい部分にまでいちいち口を出す状態を指します。
例えば、一日に何度も進捗確認をしたり、資料のフォントや表現の細部にまで修正指示を出したりといった行為です。
改善策:
このマネジメントは、プレイヤーとして優秀だった人が陥りがちです。
自分のやり方が一番正しいと思い込み、つい口を出しすぎてしまうのですが、これは部下の成長を阻害し、ストレスでメンタルを壊す原因となります。
そして、マネージャー自身の仕事量も増え、パンクしてしまう危険性もあります。
大切なのは、仕事の進め方は一つではないと認識することです。
部下にはそれぞれ合ったツールや方法があることを理解し、一度方向性を伝えたら、「信じて任せる」勇気を持つことが求められます。
3. 非現実的な締め切りが部下を疲弊させる

「この企画書、2日後までに仕上げて」と言われたものの、どう考えても4日はかかるボリュームだった――このような経験はありませんか? 無茶な締め切りは、マネージャーの根拠のない願望から来ていることが多く、現場の状況を理解せずに設定されがちです。
改善策:
非現実的な締め切りは、部下に長時間労働を強いるだけでなく、焦りから仕事が雑になる原因にもなります。
これを防ぐためには、マネージャー自身が現場を知ることが不可欠です。
実際にその仕事を経験し、一つ一つの手順や所要時間を肌感覚で把握することで、現実的な締め切りを設定できます。
また、見積もった時間に対して20%から50%程度の「余白」を持たせることも重要です。
予期せぬトラブルや緊急の仕事が入る可能性を考慮に入れ、余裕を持たせたスケジュールを組むことで、部下の疲弊を防ぎ、質の高い成果へとつながります。
4. モチベーションを奪う「マイナス指摘」の罠

「ここが足りない」「これができていない」など、部下の欠点ばかりを延々と指摘するマネジメントは、部下の自信を奪い、モチベーションを著しく低下させます。
特に、上司の一言は部下にとって想像以上に重いものです。
もちろん、改善すべき点を伝えることは必要ですが、それだけでは部下は消極的になり、しんどくなって離れていってしまう可能性が高いのです。
改善策:
重要なのは、ポジティブな評価とネガティブな評価をセットで伝えることです。
例えば、「スピード感を持って形にしたのは素晴らしい。
行動の早さは強みだと思う」と最初に褒めてから、「ただ、調査が少し浅いのと、構成に関してはもう少し工夫できそうだね」と改善点を伝えるのです。
これにより、ネガティブな指摘も受け入れやすくなり、部下は前向きに改善に取り組むことができます。
5. 理由なきプロジェクト変更が引き起こす不信感

仕事をしていると、プロジェクトの方針や指示が変更されることは珍しくありません。
しかし、「ごめん、方向性が変わっちゃって、進めてもらった件はなしになりそう」と、理由を教えられずに変更を告げられると、部下は「なぜ?」「これまでの努力は無駄だったのか」と感じ、モチベーションを失ってしまいます。
そして「どうせまた変わるんだろう」と諦めの気持ちが生まれることもあります。
改善策:
プロジェクトが変更になった際は、その理由を部下にしっかりと説明することが大切です。
変更の背景や判断に至った経緯を伝えることで、部下は納得し、モチベーションの低下を防ぐことができます。
また、これまでの努力をねぎらう一言、「正直、短期間でよくここまでまとめてくれたと思っているよ。
本当にありがとう」といった言葉を添えることで、部下との信頼関係を深めることができるでしょう。
6. 休日・時間外連絡が部下の心を削る

メールやチャットで手軽に連絡が取れる現代において、休日や業務時間外に部下へ連絡を取ってしまうことはありませんか?例えば、部下が休日に家族と過ごしている時に仕事の連絡をしてしまうと、一気に仕事モードに引き戻され、せっかくのリフレッシュが台無しになってしまいます。
日本では「休日でもすぐ返信する人がやる気ある」と評価されがちですが、これは心身の健康を損なう異常な状態だという認識が必要です。
改善策:
部下にもプライベートの時間があり、心身のリフレッシュが不可欠です。
原則として、休日や業務時間外に緊急性のない連絡は避けるべきです。
もしどうしても連絡が必要な場合は、「時間外に失礼します。急ぎではありません。
対応は休日明けで大丈夫です」といった一言を添えるだけで、部下の負担感は大きく軽減されます。
これは、部下の生活を尊重し、健全なワークライフバランスを促す上で非常に重要な配慮です。
7. 部下のミスを過剰に責めていませんか?

部下のミスに対して、感情的に責めたり、過剰に罰を与えたりしていませんか?ミスをするたびに叱責されると、部下はますます消極的になり、最悪の場合、怒られることを恐れてミスを隠そうとするようになります。
そもそも仕事におけるミスは、交通事故と同じで、どれだけ注意していてもゼロにすることはできません。
改善策:
大切なのは、ミスが発生した際に「誰のせいか」ではなく、「なぜミスが起きたのか」、そのプロセスや環境に目を向けることです。
例えば、チェック体制が甘かったのか、業務量が多すぎて集中できない状況だったのか、といった原因を特定し、ミスが起きにくい構造を作る方がはるかに建設的です。
ミスは改善のチャンスと捉え、部下が正直に報告してきた際には、まず「隠さずに言ってくれてありがとう」と、その勇気をねぎらい、受け止める度量を持ちましょう。
8. アウトプット放置が部下を不安にさせる

マネージャーにとっては、部下が提出した仕事はプロジェクト全体のごく一部に過ぎないかもしれません。
しかし、部下にとっては、それが自分の努力の全てであり、どのように評価されるのか、非常に気にしているものです。
提出してから数日経っても何のリアクションもないと、部下は「ダメだったのかな」「自分は見られていないのか」と不安になり、モチベーションが下がってしまいます。
改善策:
部下を不安にさせないために、アウトプットに対してはできるだけ早くフィードバックを返すことが重要です。
ここで言うフィードバックは、詳細な内容でなくても構いません。
「受け取りました、後で確認しておきます」や「軽く見たけどいい感じです、チェックしておきます」といった軽い一言で十分です。
この一言があるだけで、部下は「ちゃんと見てくれている」「自分の仕事は無駄じゃなかった」と安心し、次の業務への意欲を保つことができます。
その後、時間がある時にじっくりと内容を確認し、具体的なフィードバックを伝えれば良いのです。
まとめ:知識を定着させる最後のインプット

プロジェクトマネージャーとしての長年の経験を持つ橋本正吉さんの著書『人が壊れるマネジメント』から、私たちが避けるべき「ダメなマネジメント」の典型的なパターンを8つご紹介しました。
これらは、部下の心身の健康やチームの生産性に直結する重要な視点です。
- 曖昧な指示は具体的に、6W2Hを意識する。
- マイクロマネジメントは避け、部下を信じて任せる勇気を持つ。
- 非現実的な締め切りは、現場を知り、余裕(余白)を持って設定する。
- マイナス指摘だけでなく、ポジティブな評価もセットで伝える。
- プロジェクト変更の際は、必ず理由を説明し、部下をねぎらう。
- 休日や時間外の連絡は避け、緊急時も配慮の言葉を添える。
- 部下のミスを過剰に責めず、プロセスや環境改善に目を向ける。
- アウトプットには、可能な限り早く「見たよ」という軽いフィードバックを返す。
これらの知識を頭の片隅に置くだけでなく、日々のマネジメントに積極的に取り入れていくことが、向上心のある皆さんの次なるステップに繋がります。
ぜひ、この備忘録を繰り返し読み返し、実践することで、部下との信頼を深め、チームを成功に導く真のリーダーとしてさらに成長してください。

「貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する」は、お金に関する常識を覆し、新たな生き方を提示する。この記事では、本書で紹介される実践的な方法を通じて、豊かさを手にするステップを具体的に紹介します。
貧乏から豊かさへ、「雇われない生き方」で格差社会を超越する方法

あなたは『原因自分論』という考え方をご存知でしょうか?『原因自分論』という考え方は、悩んでいる物事を好転させるきっかけになる考え方です。この考え方を身に付けることができればストレスなく生きていけることはもちろん、人間関係、会社の業績、その他いろいろな物事をより良い方向に近づけていけます。
あなたを救う『原因自分論』という考え方。

多くの20代は"あれも欲しい"、"これもやりたい"とむやみに選択肢を増やして、本来必要でないことにまで貴重な時間やお金を浪費しているのではないでしょうか? そしてその全てを大事にしようとして、いろいろなものを捨てられなくなり、結果として雁字搦めになってしまっています。 本記事では自由な生き方を失わないために捨てるべきことが分かりやすく解説しています。
20代で捨てるべきもの・考え方 “8選”

『サイコロジー・オブ・マネー』は、お金に対する心構えや行動がどのように「富」に影響を与えるのかを深く探ります。本記事ではそのエッセンスを要約し、長期的に財産を築くための心理的アプローチを説明します。